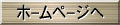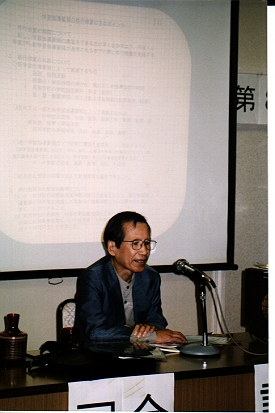第5回総会・第8回学習会報告 「総合的な学習の時間を考える」(要旨)
第5回総会・第8回学習会報告 「総合的な学習の時間を考える」(要旨)
〜1999年8月8日 東京神楽坂エミール〜
<記念講演>
「総合的な学習の時間と学校教育上の課題」
下村哲夫教授(早稲田大学)
臨教審答申から12年、教育ビッグバンといわれる今日、国は、21世紀を展望して「生きる力」の育成に向けて、学習指導要領に「総合的な学習の時間」を創設し、来年度から移行期に入る。学校裁量が大幅に増える中で教科の枠を超えて全校で取り組まなければならないのだが、果たしてみんなでやろうということになるのだろうか。
「総合」の教育は今まで3回取り組んでいずれも失敗か立ち消えに終わっている。昭和40年代のティームティーチングが「総合的な学習の時間」のイメージをもつのには最も近いだろう。しかし、本当に「生き方」学習ができなければ、定着せず次の改訂では消えることになりかねない。教育改革は上からではなく下から進めなければ本物にはならない。先生方の努力に期待するしかないが、流行に流されず、先を急ぐことなく、特に高校では平成15年度の移行期にしっかり学習ができるような、学校の体制づくりに今は努力することがいいと私は思う。
教育ビッグバンは、学級・学年解体の方向に進んでいる。学習集団が柔軟化すればするほど、子どもに暮らしの場を保障し、心の安定を与えるホームルームティーチャーの役割が大きくなる。これからますます学級担任の役割が重要になってくるだろう。
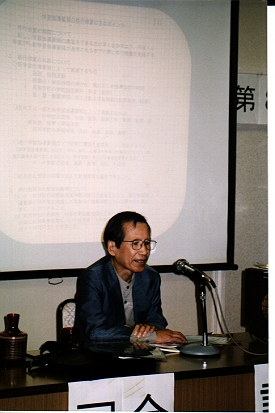

下村先生の講演 下村先生のOHPを使った講演の様子
<実践践報告>
「Action Now!!〜生きる力「人間力を育むために〜
『生き方体験学習』 盛岡・岩手・日本 NO1を探そう」
岩手県盛岡市立北松園中学校 木村幸治校長・菊池靖教諭
盛岡市の郊外にある本校は、4年前の新設当時から父母地域の人々とともに教職員あげての「生徒が主人公」という学校づくりに取り組んできた。『よりよく生きる力』と『まわりと調和していく力』の二つを「人間力」と定義し、この力を育むため、体験学習の研究的実践を進めている。
盛岡(1年)・岩手(2年)・日本(3年)と、次第に範囲を広げてNO1を探す調査活動を展開している。NO1の人々にじかに触れ、人の生き方を学び、人との関り合いや自分の人生の指標をつかもうとする学習である。合わせて、福祉体験学習(1年)・職場体験学習(2年)・高校体験入学(3年)を行っている。
3年生の『日本NO1』は、東京の修学旅行の中で行っているが、「衆議院議長面会」を実行した生徒のグループもあった。
この体験学習の結果、生徒たちは学力だけを基準とせず自分の夢に合致した高校選びをするようになったり、期せずして地域の施設の改善をうみ出したりしている。
北松園中学校の取り組みは、まさに「総合的な学習の時間」の先導的実践といえるものでした。講演で下村先生ご指摘のように、生きる力を育む「総合」の教育は自律的な教師の組織的な活動によって可能になるのだということを実感しました。


菊池先生(左)と木村校長先生(右) 北松園中学校の先生方が
実践してきた学校作りの方法
を紹介した本。ご一読を。
(明治図書より 1900円+税)
詳しい報告は、「Home Room」1月号(12月発売)に掲載されます。参加者は52名でした。